看護師のあなたは多飲水や水中毒の患者の看護で悩んでいませんか?
こんな疑問にお答えします!
・多飲水・水中毒を学ぶおすすめの本がわかる
・多飲水・水中毒の具体的な看護計画を立案する方法がわかる
この記事を書いた人
しま|精神科看護師
看護師歴10年以上。精神科病棟と精神科訪問看護を経験。転職歴は3回経験あり。現在は精神科閉鎖病棟で勤務中。Instagramもやっています。お気軽にお問い合わせやSNSのDMよりご相談ください。
この記事を書いた人
しま|精神科看護師
看護師歴10年以上。精神科病棟と精神科訪問看護を経験。転職歴は3回経験あり。現在は精神科閉鎖病棟で勤務中。Instagramもやっています。お気軽にお問い合わせやSNSのDMよりご相談ください。
結論から言うと
・多飲水や水中毒について学びたい
・多飲水や水中毒をアセスメントしたい
・具体的な看護や支援方法が知りたい
という方にはこちら、
\配送料無料・最短翌日配達!/
著:川上宏人, 著:松浦好徳, 編集:川上 宏人, 編集:松浦 好徳
¥2,860 (2025/02/02 15:29時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ
がおすすめです!
この記事を最後まで読むことで、
「多飲症・水中毒 – ケアと治療の新機軸」がなぜおすすめなのかわかり、あなたは口渇や多飲水の患者の看護計画を迷わずに立案することができるようになります!
それでは詳しく見ていきましょう!
目次
医学書院「多飲症・水中毒 – ケアと治療の新機軸」【本の紹介】

| 本について | 詳細 |
|---|
| タイトル | 多飲症・水中毒 – ケアと治療の新機軸 |
| 著者 | 川上宏人,松浦好徳 |
| 出版社 | 医学書院 |
| 価格 | 2,600円(税抜き) |
\配送料無料・最短翌日配達!/
多飲症・水中毒 – ケアと治療の新機軸|おすすめポイント
おすすめポイント|①多飲症と水中毒の知識はこれ一冊で完結
医学書院「多飲症・水中毒 – ケアと治療の新機軸」のおすすめポイントとして、「多飲症と水中毒の知識はこれ一冊で完結」しているということです。
今まで私は、副作用としての口渇や多飲水のある患者にどう向き合えばいいか、どう看護したらいいか悩んでいました。
そんな中出会ったのが、この一冊。
私がこれに出会ったのは病棟の本棚に無造作に置いてあったものをたまたま見つけ、手に取ったところからです。
発行は2010年で10年以上も前の本にはなりますが、多飲症や水中毒でこれを超える書籍は正直みたことがありません。
多飲症は飲む水分量を減らす、制限するだけでいいのではないかと思っていましたが、本書では考え方が全く違います。
ほかの書籍とは明らかに異なった多飲症や水中毒のQ&Aからはじまり、実践編、知識編とつながっていく本書の内容。
この本を通して基本的な考え方を理解したことで、患者とともに「水とうまく付き合う」方法を見出してくれた一冊です。
\配送料無料・最短翌日配達!/
おすすめポイント|②多飲症と水中毒の具体的な介入方法が学べる
医学書院「多飲症・水中毒 – ケアと治療の新機軸」のおすすめポイントとして、「多飲症と水中毒の具体的な介入方法が学べる」ということです。
多飲症や水中毒の患者に対して、どのように介入していいかわからないと思ったことはありませんか?
本書の中では医学的なエビデンスをもとに、具体的な多飲症看護の方法が提案されています。
- 行動観察…観察ポイント
- 体重測定…実際の体重の推移を確認
- 申告飲水…患者が飲水することをスタッフに申告してから飲む
「多飲症・水中毒―ケアと治療の新機軸」より一部抜粋
この一冊で多飲症患者に対して、
・どのような視点で観察するか
・どのように看護介入・支援していくか
が学べます!
\配送料無料・最短翌日配達!/
おすすめポイント|③看護計画について詳しく掲載されている
ここまで読み進めてきて、「それでも具体的な看護計画は自分で立てないといけないのでしょう」とお困りではないでしょうか?
医学書院「多飲症・水中毒 – ケアと治療の新機軸」のおすすめポイントとして、「看護計画について詳しく掲載されている」ということです。
多飲症(標準)看護計画
#1:多飲症による低ナトリウム血症、さらに水中毒発作への可能性がある。
目標
- 多飲行動が改善する、少なくなる。
- NDWG(日内体重変動)の改善が見られる(±3kg以内)。
- 水中毒発作が見られない。
- 申告飲水が行える。
O-P
- 行動(飲水行動、衣類の濡れ、食事摂取状況、排泄・睡眠状況、生活リズム)
- 発言(飲水に関すること、患者の関心や興味、入院生活全般など)
- 体重変動(主に NDWG 値の変動)
- 検査データ(血清電解質、尿比重など)
- 病歴(過去の多飲状況、水中毒発作の既往歴・生活状況)
- 精神症状の有無(焦燥、易刺激性など)
- 神経症状の有無(嘔吐、四肢振戦、てんかん発作など)
T-P
- 飲水に関する訴えを十分に聞き、患者の思いを受け止める。
- 作業療法やレクリエーション、活動行事への参加を促す。またグループ活動の導入により、「水」以外のことに関心が持てるようにはたらきかけながら患者と接点を持つ。
- 飲水を自制でき体重が減少するなど、自己コントロールできたときには、ほめたりはげまし
の声掛けを行う。
- 体重測定を1日複数回(起床時、9:30、13:30、16:00、19:30)行い、その変動を把握する。
- 精神症状悪化時や神経症状出現時は、患者の体重測定値を考慮の上、早期に主治医
もしくは当直医に報告する。
E-P
- 多飲による身体への影響を説明する。
- 上手な飲水の方法や、1日にどの程度飲めるのかを患者と共に考えながら指導する。
- 申告飲水を指導する。
<*主に多飲症心理数育プログラムにおいて指導するが、日々のかかわりのなかで受け持ち
看護師が中心となり指導を適宜実施する)
多飲症・水中毒 – ケアと治療の新機軸より
目標は「多飲症」という行動の改善であり、それができれば「水中毒」は起きないという考えのもと立案されています。
- 身体拘束は避ける
- 多飲症患者がオープンに飲水できる環境を作る
- 多飲症は飲水量のみで決めない(ベース体重で確認をする)
といった単純な飲水制限ではなく、行動にフォーカスした介入・支援方法を本書は提案しています。
医療側が一方的に制限することで患者が不快な思いをするのではなく、一緒に計画をたてて行動することでよりアドヒアランスの高い介入・支援に繋がります!
\配送料無料・最短翌日配達!/
多飲症・水中毒 – ケアと治療の新機軸|まとめ

結論から言うと
・多飲水や水中毒について学びたい
・多飲水や水中毒をアセスメントしたい
・具体的な看護や支援方法が知りたい
という方にとてもおすすめの本です。
この1冊で、口渇や多飲水の患者の看護計画を迷わずに立案することができるようになるためおすすめです!
購入はこちらからどうぞ↓
\配送料無料・最短翌日配達!/
著:川上宏人, 著:松浦好徳, 編集:川上 宏人, 編集:松浦 好徳
¥2,860 (2025/02/02 15:29時点 | Amazon調べ)
 ポチップ
ポチップ




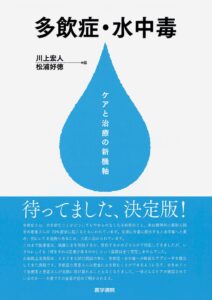



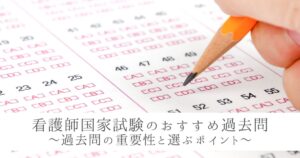
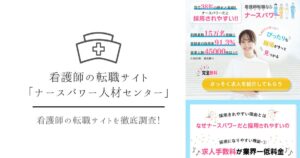



コメント