精神科の「入院形態」は、患者さんの状態や同意の有無によって異なる5つの種類に分けられています。
国家試験でも頻出のテーマであり、現場で働く看護師にとっても患者の人権や安全を守るための重要な知識です。
種類は多くてもポイントを抑えれば意外と簡単なので、一緒に確認しましょう!
この記事では、精神保健福祉法に基づく5つの入院形態を、法律・看護の視点からわかりやすく解説します。
・入院形態の違いがわかる
・入院形態の違いによる看護の視点がわかる
看護学生や若手看護師の方が、国試対策にも現場実践にも役立つように整理しました。
目次
精神科における入院形態とは
精神科の入院形態は、大きくは「本人の同意の有無」と、「入院の必要性を判断する医師(指定医)の判断」によって区別されます。
入院形態としては、
・任意入院
・医療保護入院
・措置入院
・緊急措置入院
・応急入院
の5つがあり、それぞれに法的根拠と手続きが定められています。
精神保健福祉法によって定められたそれぞれの入院形態にあわせて、患者の人権を尊重しながら適切な医療を提供することが求められています。
精神科の入院形態5つの種類と特徴
① 任意入院
「任意入院」とは、患者本人の同意に基づく入院形態です。
自発的に「入院して治療を受けたい」と意思表示できる場合に行われ、もっとも自由度が高い入院形態です。
退院の希望も原則として本人の意思で可能ですが、病状によっては医師の判断で一時的な制限がかかることもあります(退院制限)。
看護のポイントとしては、治療への動機づけを支援し、自己決定を尊重した関わりが求められます。
また、仮に任意入院であっても病状によっては隔離や身体拘束など行動制限を要する状態に至ることがあります。
その場合には、適切な入院形態へ変更する必要があります。看護師の状態観察は非常に重要になってくるため、適切な観察を行い、客観的な情報を報告し、主治医・指定医の判断を仰ぎましょう。
② 医療保護入院
「医療保護入院」とは本人の同意が得られない場合に、「精神保健指定医1名の診察と家族等の同意」によって行われる入院です。
「自傷他害のおそれはないが、任意⼊院を⾏う状態にない」と判断されたときに適用されます。
また、家族等の同意は三親等以内の者の同意が必要となります。
本人自身の同意ではない入院形態であるため、外出等の自由が制限されます。看護師は患者の不安や混乱を軽減し、治療の必要性の説明や患者との信頼関係を築くことが大切です。
③ 措置入院
「入院させなければ自傷他害のおそれのある」と判断された場合に、都道府県知事の権限で行われる入院です。
2名の精神保健指定医が「入院の必要あり」と診断した場合に実施され、患者の意思にかかわらず強制的に行われます。
社会的に安全を守る目的も含まれるため、看護師は安全確保と人権擁護の両立を意識する必要があります。
退院は医師の判断に基づいて都道府県知事の決定(措置解除)が必要となります。
④ 緊急措置入院
措置入院が必要と判断されるが、2名の指定医の診察を待つ時間がないほど緊急性が高い場合に行われます。
1名の精神保健指定医の診察で入院を決定し、72時間以内に限り入院させることができます。
緊急措置入院後は、速やかに措置入院の要否について決定しなければいけません。
そのため、この72時間以内という期限が過ぎる前に指定医2名の診察を行い、正式な措置入院へ切り替えるか措置不要と判断されます。
看護師は急性期のリスクアセスメントを行い、安全な環境整備と観察を徹底します。
⑤ 応急入院
「入院を必要とする精神障害者で、任意入院を行う状態になく、急速を要し、家族等の同意が得られない者」に関して、医療が必要であると判断されたときに、指定医1名の診察で72時間以内の入院を認める制度です。
「医療保護入院の緊急版」とも言え、患者の安全確保を目的としています。
72時間を超えて入院を継続する場合は、家族の同意などを得て医療保護入院に切り替える必要があります。
看護師は短期間での観察とアセスメントを行い、退院・転院を見据えた支援が求められます。
図でわかる入院形態の比較
| 入院形態 | 同意者 | 指定医 | 期間 | 特徴 |
|---|
| 任意入院 | 本人 | 1名 | 制限なし | 本人の意思で入退院が可能 |
| 医療保護入院 | 家族等1名 | 1名 | 制限なし | 本人同意なしでも入院可 |
| 措置入院 | なし(知事権限) | 2名 | 制限なし | 自傷他害の恐れがある場合 |
| 緊急措置入院 | なし(知事権限) | 1名 | 72時間以内 | 緊急時の措置入院準備 |
| 応急入院 | 同意者なし | 1名 | 72時間以内 | 保護者同意が得られない緊急時 |
看護師が知っておくべき法的視点
入院形態はすべて「精神保健福祉法」に基づいており、患者の権利保護が基本にあります。
同意が得られない入院であっても、患者の尊厳を守り、最小限の制限にとどめることが重要です。
看護師は「隔離」「身体的拘束」などの行動制限との違いや手続き上の流れを理解し、倫理的判断を伴う支援を行う必要があります。
現場で役立つ看護の視点
入院形態によって、看護の視点は異なります。
任意入院では自己決定の尊重、医療保護入院では家族支援、措置・緊急入院では安全確保と人権擁護が大切です。
例えば、任意入院患者は閉鎖病棟であっても日中は開放的な処遇を受ける権利があります。
しかし、医療保護入院患者は制限がかかることが多く、医師の指示によって制限が生じることが少なくありません。
看護師は患者の不安・恐怖を軽減し、安心して治療に臨める環境づくりを心がけましょう。
また、法的手続きや書類管理などの事務的要素も正確に理解しておくことが求められます。
入院形態に関するFAQ
- 精神科の入院形態は全部でいくつありますか?
-
精神科の入院形態は全部で5つあります。
①任意入院、②医療保護入院、③措置入院、④緊急措置入院、⑤応急入院の5種類です。
それぞれ「同意者の有無」「指定医の人数」「入院期間の制限」などが異なります。
- 精神科の入院形態の覚え方を教えてください。
-
「任医措緊応(にいしょきんおう)」と語呂で覚えるのが定番です。
任=任意、医=医療保護、措=措置、緊=緊急措置、応=応急を表しています。
また、「自由度が高い順」「指定医の人数順」で整理すると理解が深まります。
- 措置入院と医療保護入院の違いは何ですか?
-
措置入院は「自傷他害のおそれがある」場合に、都道府県知事の権限で行われる入院です。
一方、医療保護入院は「同意は得られないが医療が必要」な場合に、家族の同意と指定医1名の判断で行われます。
措置入院は社会的保護の意味合いが強く、医療保護入院は治療的目的が中心です。
- 応急入院と緊急措置入院の違いは?
-
どちらも「緊急時の一時的入院」ですが、目的が異なります。
緊急措置入院は措置入院を準備するための入院で、指定医1名・72時間以内。
応急入院は同意者がいない場合でも医療が必要なときに行う入院で、こちらも72時間以内です。
緊急措置=公的保護、応急=医療的緊急対応という違いがあります。
- 入院形態によって退院の手続きは違いますか?
-
はい、異なります。
任意入院では本人の希望で退院できますが、医療保護入院や措置入院では医師の判断が必要です。
措置入院の場合、都道府県知事の許可を経て退院が決定します。
看護師は患者・家族に退院手続きをわかりやすく説明することが大切です。
- 精神科入院形態で看護師が注意すべきポイントは?
-
入院形態ごとに患者の背景や制限の程度が異なるため、
「どのような法的根拠で入院しているか」を理解した上で関わることが大切です。
任意入院では治療意欲の支援、医療保護入院では家族支援、措置入院では安全確保と人権配慮が重要です。
- 国家試験ではどんな点がよく出題されますか?
-
国家試験では「指定医の人数」「同意者の有無」「72時間以内」などの法的手続きが頻出です。
特に措置入院と医療保護入院の違い、応急入院と緊急措置入院の区別は毎年のように出題されています。
表で比較して覚えると効率的です。
まとめ|入院形態を理解することの重要性
入院形態は単なる分類ではなく、患者の権利・安全・治療方針に直結する制度です。
看護師として、法的理解と人間理解の両方を持つことが大切です。
国家試験対策としてだけでなく、現場での看護判断の基礎として、入院形態をしっかり整理しておきましょう。
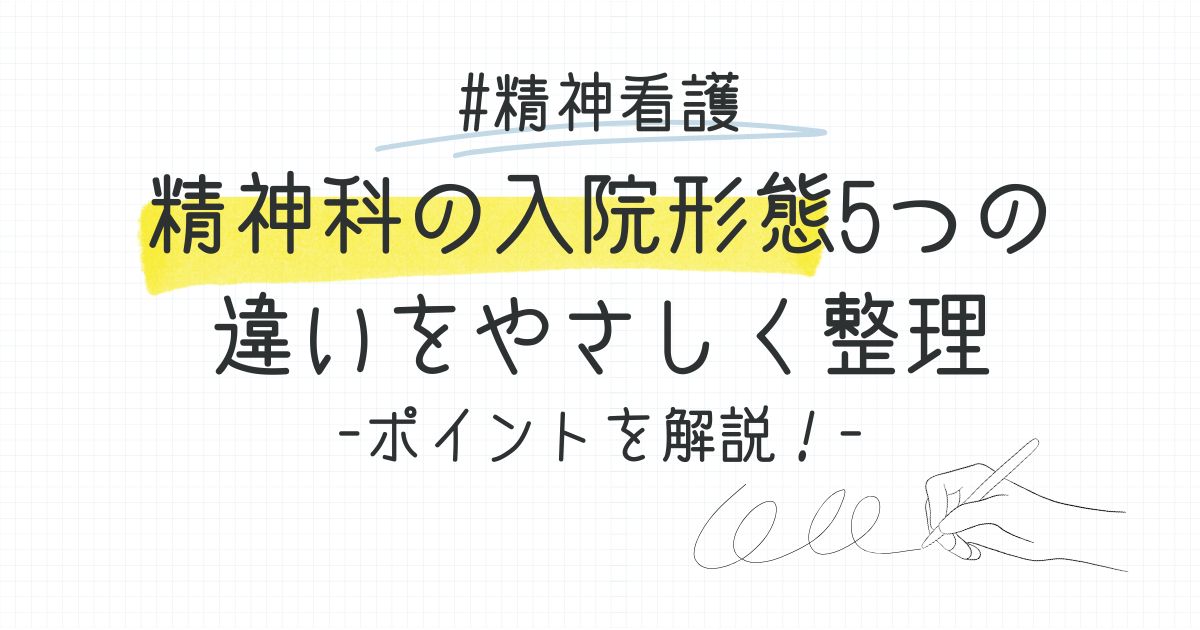

コメント