「退職したい!」そう思ったときに、最初に悩むのが 「退職届と退職願、どっちを出せばいいの?」 という問題ではないでしょうか?
似たような言葉ですが、この2つは会社に与える意味が大きく違います。間違った方を提出すると、「退職の話がこじれる」「辞められない」といったトラブルに発展する可能性もあります。
✔ 退職届と退職願の違いは何か?
✔ どんなケースでどちらを使うべきか?
✔ 円満退職をするための正しい手順とは?
この記事では、こうした疑問を解決しながら、スムーズに退職するための方法を分かりやすく解説していきます。
「スムーズに会社を辞めたい!」「円満に退職したい!」と考えているなら、ぜひ最後まで読んでくださいね。
目次
退職届と退職願の違いとは?
1-1. 退職届とは?
退職届は、「退職を確定させるための書類」です。
会社に提出すると、基本的には撤回ができず、正式に退職が決定します。
会社側も「受理した以上は退職を認めなければならない」ため、強い効力を持つ書類といえます。
1-2. 退職願とは?
退職願は、「退職を願い出るための書類」です。
会社側が承認しなければ効力が発生せず、撤回することも可能です。
つまり、「退職の意思はあるけれど、会社と話し合いながら円満に進めたい」という場合に使う書類になります。
1-3. 退職届と退職願の決定的な違い
| 項目 | 退職届 | 退職願 |
|---|
| 意味 | 退職を確定させる書類 | 退職を申し出る書類 |
| 会社の対応 | 受理したら拒否できない | 会社の承認が必要 |
| 撤回の可否 | 基本的に不可 | 会社の許可があれば可能 |
| 使うケース | 退職を確定させたいとき | 会社と相談しながら進めたいとき |
このように、退職届と退職願は「確定させるか」「話し合う余地を残すか」という点が大きな違いになります。
1-4. 会社に提出するならどっちが正解?
基本的には「退職願 → 会社の承認 → 退職届提出」の流れがベストです。
いきなり退職届を提出すると、「円満退職」にならない可能性もあります。
一方で、「もう会社と話し合う余地がない」「退職の意思を強く示したい」という場合は、最初から退職届を出してもOKです。
1-5. 退職届・退職願の書き方のポイント
書き方のポイントは以下の3つです。
- シンプルで簡潔に書く(長々と理由を書く必要はありません)
- 提出日・退職日を明記する(退職日は就業規則を確認)
- 宛名は「代表取締役」(直属の上司ではなく会社のトップ宛にする)
退職届と退職願の使い分け!ケース別の正しい選び方
2-1. 円満退職を目指すなら退職願
退職後も関係を良好に保ちたい場合は、退職願を提出しましょう。
退職願なら「上司と相談しながら進める余地がある」ため、会社に迷惑をかけず円満退職しやすくなります。
2-2. 会社とトラブルを避けるなら退職届
退職の話し合いが難航しそうな場合や、確実に退職したい場合は、退職届を提出した方が安心です。
特に、ブラック企業の場合は「退職願では退職を認めてもらえない」こともあるため、退職届を出して確定させるのが得策です。
2-3. 退職理由による適切な選択方法
- 自己都合退職 → 退職願を出して円満に進める
- 転職が決まっている → 退職届を提出し、退職日を確定させる
- ブラック企業で辞めにくい → 退職届を送付し、弁護士や退職代行を活用する
2-4. 有給消化を希望する場合の注意点
退職届や退職願を出す前に、有給消化について会社と交渉しましょう。
退職日まで有給を使うつもりなら、退職届を出す前に「有給消化が可能か」を確認しておくことが重要です。
退職届・退職願を出す前に押さえるべき注意点
3-1. 提出するタイミングと手順
退職の申し出は「1ヶ月以上前」が一般的です。
就業規則によっては「2ヶ月前」「3ヶ月前」と決まっている場合もあるので、事前に確認しましょう。
3-2. 退職を拒否されたときの対応策
退職は法律上の「自由」です。
拒否された場合は「退職届を内容証明郵便で送る」「労働基準監督署に相談する」などの方法を検討しましょう。
3-3. 退職届・退職願の撤回は可能?
退職願なら会社の許可があれば撤回できますが、退職届は基本的に撤回不可です。
提出前によく考えてから出しましょう。
3-4. 会社に引き止められた場合の対処法
「あと半年いてほしい」など引き止められることもあります。
曖昧にせず、「すでに次の仕事が決まっています」などと明確に伝えることが大切です。
退職届・退職願の正しい書き方と提出マナー
1. 退職願のテンプレートと例文
📌 退職願の基本フォーマット
- 用紙サイズ:A4またはB5
- 記入方法:縦書き or 横書き(パソコンの場合は横書き)
- 提出時期:退職希望日の1〜2か月前が一般的
- 封筒:白無地封筒に「退職願」と記載
📝 退職願(例文:手書き用・縦書き)
私こと、このたび一身上の都合により、令和○年○月○日をもちまして
退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
令和○年○月○日
(自分の氏名)
(自分の印鑑)
株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 様
💻 退職願(例文:パソコン用・横書き)
株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 様
私は、一身上の都合により、令和○年○月○日をもちまして
退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
令和○年○月○日
(自分の氏名)
(自分の印鑑 ※手書きなら押印推奨)
📢 ポイント
- 「お願い申し上げます」と書くことで、会社の承認が必要な書類であることを明確にする
- 退職日は希望日を記載し、会社と相談の余地を残す
- 退職理由は 「一身上の都合により」 でOK!(具体的な理由は不要)
- 上司ではなく 会社の代表取締役 宛にする
2. 退職届のテンプレートと例文
📌 退職届の基本フォーマット
- 用紙サイズ:A4またはB5
- 記入方法:縦書き or 横書き(パソコンの場合は横書き)
- 提出時期:退職日の2週間〜1か月前(会社の就業規則を確認)
- 封筒:白無地封筒に「退職届」と記載
📝 退職届(例文:手書き用・縦書き)
私こと、このたび一身上の都合により、令和○年○月○日をもちまして
退職いたしますので、ここに届け出いたします。
令和○年○月○日
(自分の氏名)
(自分の印鑑)
株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 様
💻 退職届(例文:パソコン用・横書き)
株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 様
私は、一身上の都合により、令和○年○月○日をもちまして
退職いたしますので、ここに届け出いたします。
令和○年○月○日
(自分の氏名)
(自分の印鑑 ※手書きなら押印推奨)
📢 ポイント
- 「届け出いたします」 と書くことで、退職の意志が確定していることを明示
- 退職日は 会社の就業規則を確認 してから記載する
- 退職理由は 「一身上の都合により」 で十分(詳しい理由を書く必要なし)
- 提出後の撤回は基本的に不可 なので、慎重に提出する
3. 退職願・退職届の提出マナー
✅ 提出前に確認すべきこと
- 就業規則をチェック(退職希望日の○ヶ月前までに提出すべきか確認)
- 上司に口頭で事前相談(いきなり書類を出すのはNG!円満退職のためにも一度相談する)
- 有給消化の確認(退職日までの有給取得を希望する場合は、先に相談しておく)
✅ 提出時のマナー
- 退職願・退職届は 封筒に入れて提出(表に「退職願」または「退職届」と記載)
- 直属の上司に手渡し(いきなり社長や人事に持っていかない)
- 無理に引き止められたら?(「一身上の都合で退職を決意しました」とキッパリ伝える)
退職届と退職願の違いは?ケース別の使い分けと提出マナー|まとめ
退職届と退職願は似ているようで、会社に与える影響がまったく異なります。
- 退職届 … 退職を確定させる書類(撤回不可)
- 退職願 … 退職を申し出る書類(会社の承認が必要)
基本的には 「退職願 → 会社の承認 → 退職届提出」 という流れがスムーズな退職方法です。
しかし、会社がなかなか辞めさせてくれない場合や、トラブルを避けたいときは、最初から退職届を提出してしまうのも選択肢のひとつ。
また、退職を申し出るタイミングやマナーも重要です。 「退職日はいつにするのか?」「有給消化は可能か?」 など、事前にしっかり準備をしておきましょう。
退職は人生の大きな決断。だからこそ、正しい知識を持ち、後悔のない形で会社を去ることが大切です。
「これから退職を考えている」「どう進めたらいいか不安」という方は、この記事を参考にして、スムーズに退職手続きを進めてくださいね!
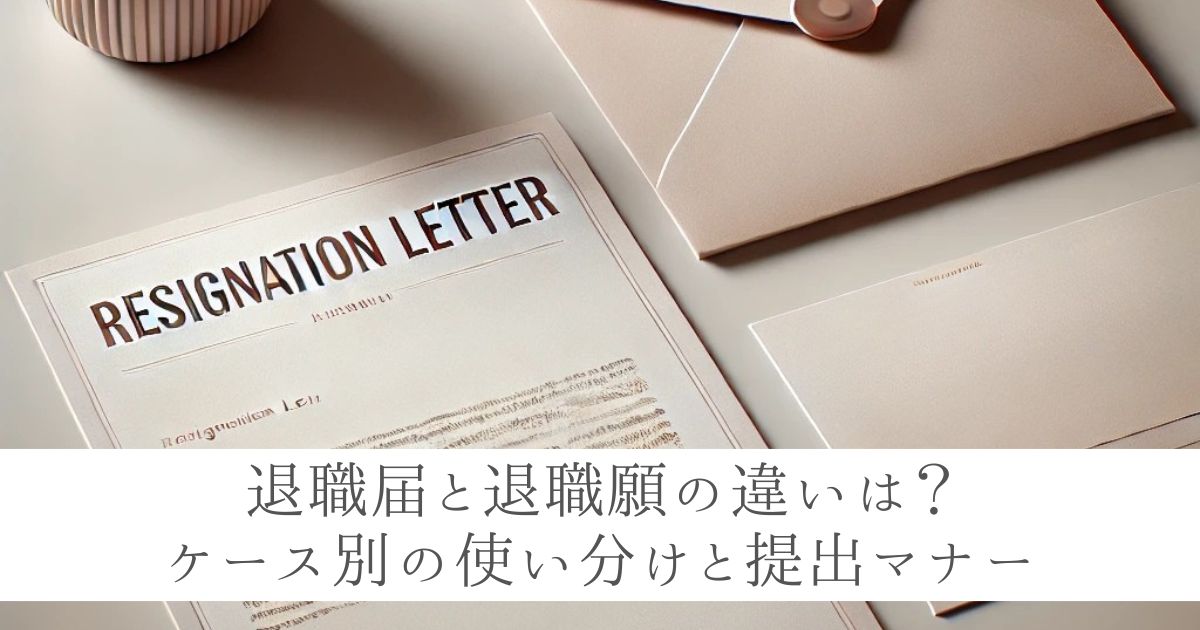
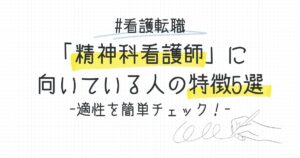


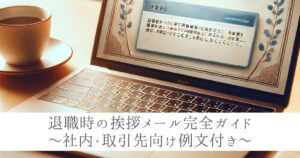
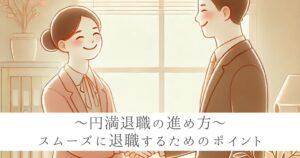



コメント